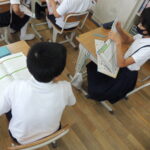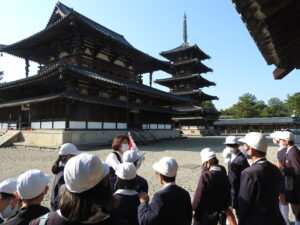12月10日(金)、6年生が中心となり、リモート(Google Meet)を使って、全校でお楽しみ会を行いました。オープニングは、神レンジャーの登場です。神ぞうも出てきて、クリスマスのお話をしました。子どもたちは各教室のスクリーンに映った神レンジャーたちの姿を見て、笑顔一杯です。その神レンジャーたちが、各学年・学級の教室にいるみんなの前に現れました。「サンタさんのお願い(船長さんの命令ゲーム)」、「○×ゲーム」そして、「サンタさんがやってくるゲーム」で楽しく遊びました。6年生の先生のじゃんけんもあり、先生方も楽しみました。児童代表の挨拶や司会・進行、ゲーム、BGM、神レンジャー出演、声優、各教室での指示など役割を分担し、「神岡小学校のみんなが楽しく、笑顔になるように」という思いで、準備し、進めました。2学期の終わり、みんなに元気を届け、大成功でした。各教室には学級で作ったツリーの飾り付けもありました。最後に6年生に、各教室から感謝の拍手を送り、締めくくりました。